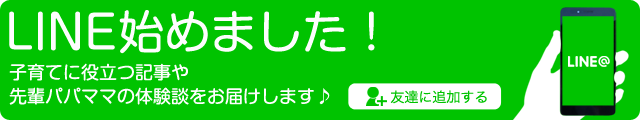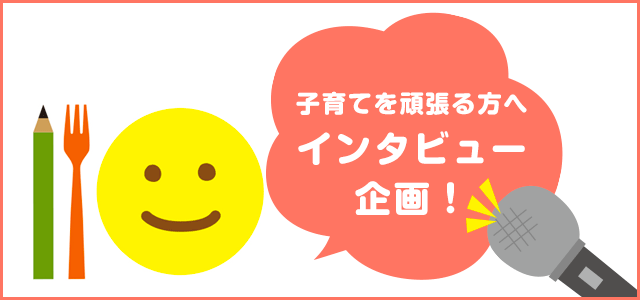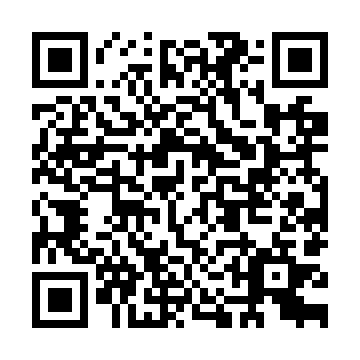- 子育てノウハウ
- 1歳〜2歳
体の発達に合った良いおもちゃで子どもの可能性を引き出す!

子どもに与えるおもちゃは、どんなおもちゃがよいのでしょうか?
それはまず、子どもが興味を持ってくれること。そして、次にそのおもちゃが子どものさまざまな能力を引き出してくれること。この条件を満たすおもちゃは、子どもにとってよいおもちゃといえます。3歳以下の子どもに、そんなよいおもちゃを選ぶためのポイントと注意をまとめてみました。
おもちゃの目的は、子どもが遊ぶこと

子どもが遊べるよいおもちゃというのは、子どもの発育に合ったおもちゃです。例えば3か月から6カ月の子どもに与えるおもちゃは、赤ちゃんの小さな手でも握れること、口に含んでも安全で誤飲をしない大きさであること、寝返りやお座りができる程度の発育状態ですから、赤ちゃんの筋力でいじれる形や重さでなければなりません。
また、動作も引っ張ったり、掴んだりと、赤ちゃんは丁寧におもちゃを扱えないので、壊れやすいものもダメです。一般的には、ガラガラやおしゃぶり、ぬいぐるみなどがこの月齢に向いているおもちゃといえます。
子どもが1歳近くになると、モノを掴んで、投げたり、押したりといった大きな動作ができるようになります。音楽にも反応をし始めるので、ボールや積み木、太鼓などが適しています。また、自分が好きなおもちゃという意識が芽生えるのもこの頃です。
このように、子どもの発育によって遊べるおもちゃは異なっており、1歳の子どもに0歳のおもちゃを、逆に0歳に1歳の子どものおもちゃを与えても、おもちゃは遊ぶという目的を果たしません。いくら高価なおもちゃでも、子どもの月齢に合ったものでなければ、子どもが遊ぶことができないため、よいおもちゃ選びとはいえません。
絶対に壊れないおもちゃはない

3歳児以下に与えるおもちゃは、特に丈夫でこわれにくいということが必須です。子どもの動きは激しいですし、丁寧な扱いもできません。壊れやすいおもちゃでは、遊びが中断されるだけでなく、危険を伴います。また、子どもの動きは、大人の想定をはるかに超えていますから、絶対に壊れない安全なおもちゃは存在しないと、親は常に注意を払う必要があります。
大抵の場合、事故は子どもの行動パターンと連動しています。普段から、モノを振り回すくせのある子どもに、刀のようなおもちゃは事故が起こる危険が高いですし、モノを投げる子どもに、重みのあるおもちゃを渡せば、投げて他の子どもがケガをする可能性が高くなります。
自分の子どもの日常の動きをしっかりと把握しておきましょう。また、おもちゃの形状で、小さいものと先のとがったものは、年齢を問わず非常に危険ですので、子どもには絶対渡してはいけません。
素材の安全性はどうやってチェックするのか?

大きさや形は大人が目で安全かどうか、ある程度判断することができますが、使われている材質や塗料の安全性を見極めるには、一般社団法人 日本玩具協会のSTマークが参考になります。
STマークは玩具の安全性(機械的安全性、可燃安全性、化学的安全性)を示す基準として、業界が検査に合格したおもちゃに付けるマークです。このSTマークが付いたおもちゃは「安全面を注意深く考慮し、作られたおもちゃ」として業界が推奨しています。
おもちゃに限らず、一般に販売されている製品の安全性を表すものに一般財団法人 製品安全協会のSGマークがあります。自転車や三輪車には、このSGマークがついています。花火には、公益社団法人 日本煙火協会がおこなう検査に合格した国産・輸入品のおもちゃ花火に付けるSFマークがあります。
これら、STマーク、SGマーク、SFマークは、どれも業界で自主的に行われる検査ですが、これらのマークがついた商品で、明らかに商品に欠陥がありケガをした場合は、損害賠償制度が適用されます。国内で流通するおもちゃの安全性はこれらの安全マークが目安になるでしょう。
また、最近は輸入品のおもちゃも手軽に購入できるようになりました。EU加盟国には安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすCEマークというものがあります。日本のおもちゃでも、海外に輸出される商品には、このマークがついているものもあります。
おもちゃは子どもに夢を与えるもの

よいおもちゃは、子どもの発育に合ったサイズで、激しい動きに対応する安全なものであることはもちろんですが、子どもに夢を与えるものでなければなりません。
特に自分の好き嫌いが芽生える1歳以降は、気に入ったおもちゃへのこだわりが強くなります。また、だんだん危険で好ましくないおもちゃや、他の子どもがもっているおもちゃと同じものを欲しがったりし始めます。そんな子どもの要求に、どのように答えてあげればよいかは、安全マークでは判断できません。
与えられた子どもが、「もらってうれしい」という気持ちを汲み取るには、毎日子どもと接している親が、子どもが選ぶおもちゃの良し悪しを見極めるしかないのです。子どもの個性で、一概にはいえませんが、その時の参考として、以下の3つのポイントがあります。
- 1)実際に子どもが手に取って遊んだ経験から「欲しい」というもの
- 2)一つのおもちゃから、いろんな遊びが広がりそうなもの
- 3)自分で片づける(整理しておもちゃ箱に入れるなど)ことができるもの
自分で選んだおもちゃは、遊ぶだけでなく管理する自己責任があることを教えるいい機会になります。自分で本当に片づけることができるサイズや形、もしくはそのためのスペースを自分で作り自主的に収納することができるものを、子どもが選ぶときの基準として伝えるのもよいかもしれません。
最後に繰り返しますが、おもちゃは、子どもの心の成長を支える大切なものです。しかし、その中で悪い影響を与えるものや、トラブルを起こすものもあります。また、絶対安全なものもありません。子どもの可能性を引き出す「よいおもちゃ」の条件には、大人の見守りが必須であることは常に頭に入れておきましょう。